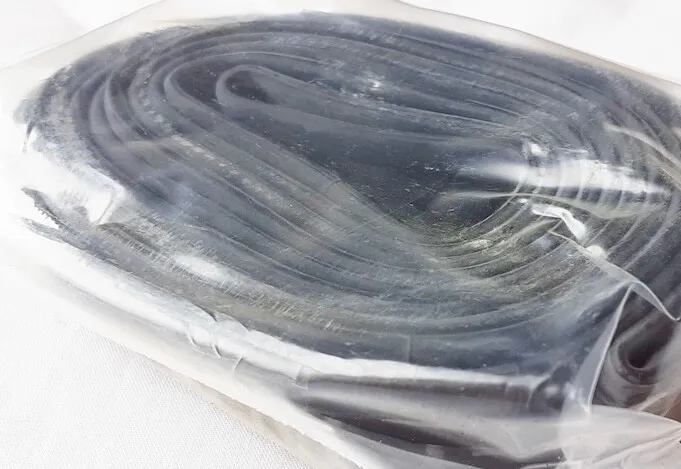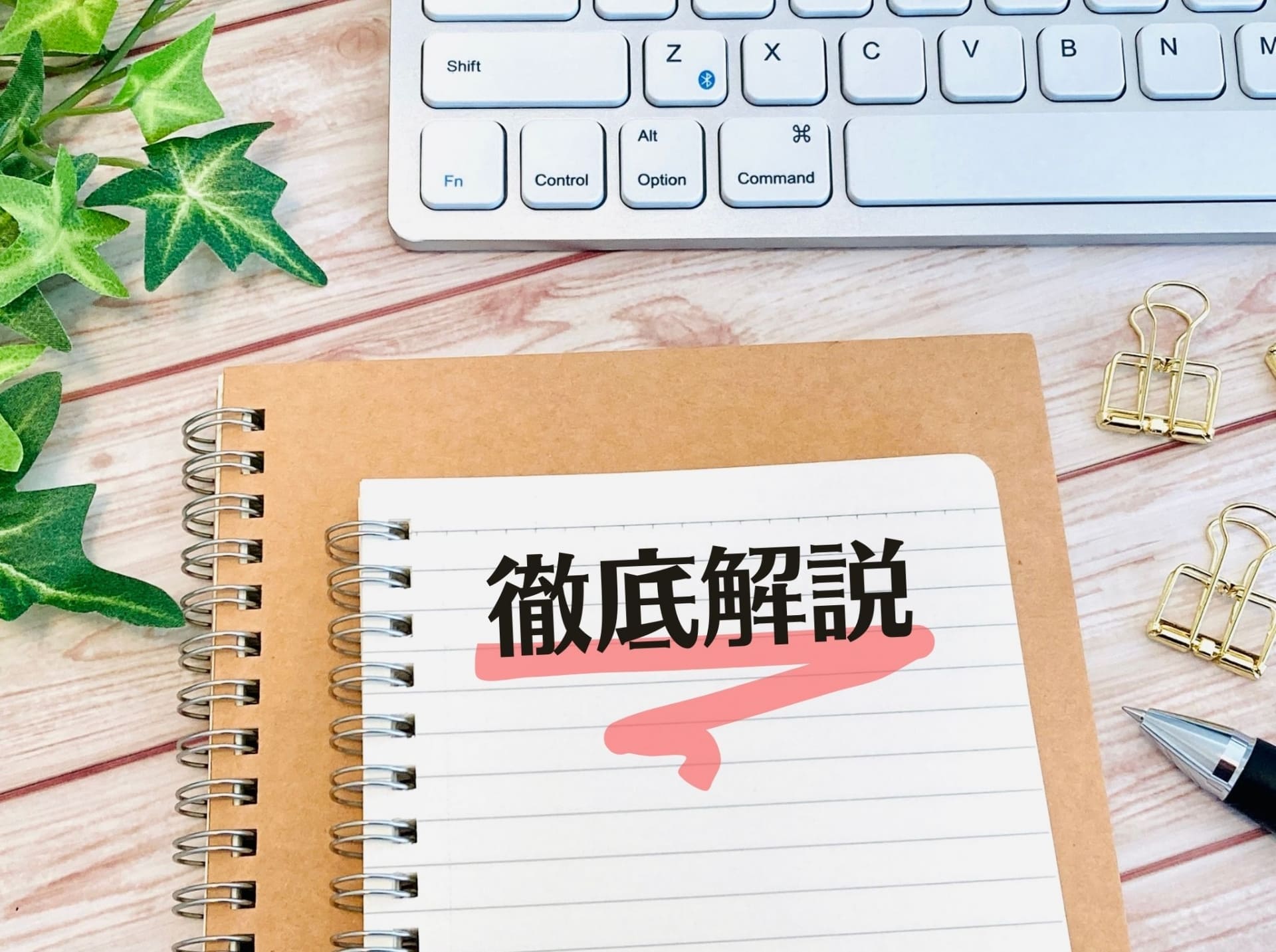製品開発や品質管理において、材料の強度試験は欠かせない工程です。しかし、引張試験機の選定は一筋縄ではいきません。「どの機種を選べば良いのか」「必要な機能は何か」「予算に見合った選択ができるのか」―。多くの企業が、これらの課題に直面しているのではないでしょうか。本記事では、引張試験機選定のポイントを、基本機能から運用面まで徹底的に解説します。自社に最適な引張試験機を見つけるための、確かな道しるべとなるはずです。
引張試験機とは?基本機能と種類を理解する
材料の強度評価に必要不可欠な引張試験機について、基本構造と機種選定の基準を詳しく解説します。基本構造では、試験片のつかみ具、力を加えるクロスヘッド、力を測定するロードセルといった重要な構成要素について説明します。また、接触式・非接触式の変位測定装置や、様々な種類の治具についても触れ、それぞれの特徴や適用範囲を明確にしていきます。さらに、最新のデジタル画像相関法(DIC)による計測技術についても紹介し、材料評価における先進的なアプローチについて解説していきます。
引張試験機の基本構造と測定原理
引張試験機は、材料の強度や変形特性を測定する精密機器です。基本構造は、試験片を固定するつかみ具、力を加えるクロスヘッド、そして力を測定するロードセルから構成されています。
ロードセルには力が加わると変形する起歪体が組み込まれており、高精度な測定が可能です。
変位測定装置は、材料の変形量を正確に計測する重要な部分です。接触式と非接触式の2種類があり、試験の目的や試料の特性に応じて選択します。特に最新の非接触式は、試料に触れることなく高精度な測定が可能になるものもあります。
試験片を固定する治具には、空気式平面つかみ具や定位置くさび式つかみ具などがあり、試験片の形状や材質に応じて適切なものを選択します。
近年では、デジタル画像相関法(DIC)による変位計測も可能になり、より詳細な材料評価が実現しています。測定データは専用ソフトウェアで処理され、材料の力学的特性を正確に把握することができます。
容量別・用途別の機種選択の基準
引張試験機の選定では、まず試験対象物の特性に応じた容量選択が重要です。金属材料の場合、試験機の精度等級(例:JIS B7721のClass 1)を満たすためには、通常その最大容量の20%以上の荷重範囲で測定を行う必要があります。そのため、試験片の引張強度と断面積をもとに、必要な荷重とそれに見合う容量を算出します。
プラスチックやゴムなどの軟質材料では、0.5kN~5kN程度の小容量機が適しています。一方、金属材料では、一般的に10kN~100kNの容量が必要となり、高強度鋼材では300kN以上の大容量機が求められます。
用途別では、研究開発用には高精度な非接触伸び計や高速データサンプリング機能が、品質管理用には操作性と耐久性が重視されます。特に自動車部品や建材の評価には、JIS規格に準拠した測定精度と再現性の高さが求められます。
また、試験速度範囲や温度環境への対応、データ処理機能など、目的に応じた機能の選択も重要なポイントとなります。
JISに基づいた引っ張り試験の種類
引張試験機の精度と信頼性を確保するために、材料ごとに規定された重要なJIS規格について解説します。金属材料、プラスチック、ゴムなど、それぞれの材料特性に応じた試験方法が定められており、試験速度や環境条件、測定項目が異なります。非接触伸び計による高精度な変位測定や、適切なチャックの選定など、正確なデータ取得のためのポイントについても触れていきます。各規格に準拠した試験を実施することで、材料の機械的特性を適切に評価することができます。
JIS Z 2241:金属材料の引張試験方法
金属材料の引張試験を行う際は、JIS Z 2241規格に準拠した方法で実施する必要があります。この規格では、試験片の形状や寸法、試験速度、データの取得方法など、詳細な手順が定められています。
試験速度については、JIS Z 2241の附属書において、ひずみ速度制御の一例として、降伏点までは毎分0.2〜2.0%のひずみ速度で、降伏点以降は毎分1.0〜10.0%の範囲が推奨されています。これにより、材料の機械的特性を適切に評価することが可能となります。
引張試験機では、降伏強さ、引張強さ、伸び、絞りなどの重要な機械的特性を測定できます。特に極限引張強度(UTS)の測定には高い精度が求められ、非接触伸び計を使用することで精密なデータ取得が可能です。
測定精度を確保するために、定期的な校正と、試験環境の温度管理(23±5℃)が重要となります。また、試験片の取り付け方法や、チャックの選定にも十分な注意を払う必要があります。
JIS K 7113:プラスチックの引張試験方法
JIS K 7113は、プラスチック材料の引張試験方法を規定する重要な規格です。試験速度は、試験片の種類や評価目的に応じて設定されます。JIS K 7113では、標準的な試験速度として50 mm/minが推奨されており、必要に応じて1 mm/minなどの低速試験や、用途によっては高速試験も行われます。
測定項目には、引張強さ、破断時の伸び、降伏点、弾性率などが含まれ、材料の機械的特性を総合的に評価します。
試験環境は23±2℃、湿度50±10%に維持する必要があり、試験前には規定された条件で試験片を調湿します。
測定の精度を高めるために、非接触伸び計の使用が推奨されます。これにより、試験片への接触による影響を排除し、より正確なデータ取得が可能となります。また、試験片の形状や寸法は材料の種類によって異なるため、規格に従った適切な選択が重要です。
JIS K 6251:ゴムの引張試験方法
JIS K 6251は、ゴム材料の引張試験方法を規定する規格で、試験速度は標準で500±50mm/分と定められています。試験機には、高い精度でロードセルによる荷重測定が求められ、高精度な計測が不可欠です。
試験環境は23±2℃の温度管理が必要で、試験前に試験片を規定の環境下で16時間以上調整します。
非接触伸び計を使用することで、柔軟なゴム材料の正確な変位測定が可能です。特に、ゴムの大きな伸びに対応するため、標点間距離の設定と測定範囲の調整が重要となります。
試験片の固定には、空気式チャックや特殊なつかみ具が推奨され、試験片の滑りや変形を防止することで、信頼性の高いデータ取得が可能です。
高精度測定のための重要機能をチェック
引張試験機の性能を最大限に引き出し、信頼性の高い測定を実現するための重要な機能をご紹介します。特に、非接触伸び計の選定基準、試験片の形状や材質に応じたチャックの選択方法、そしてデータ処理・解析機能の比較について詳しく解説します。これらの機能は、測定精度と作業効率に大きく影響するため、導入時の検討ポイントとして重要です。また、JIS規格に基づいた試験の実施や、材料特性の正確な評価にも直結する要素となります。
非接触伸び計の特徴と選び方
非接触伸び計は、試験片に直接触れることなく変位量を測定する先進的な装置であり、試料への影響を排除できるため、フィルムや箔、細線材などの繊細な材料に適しています。
最新の機種では、伸びの計測精度でISO 9513 Class 0.5(JIS B 7741 0.5級)に準拠しており、高精度な試験に対応可能です。
機器選定にあたっては、測定対象の材質や形状に応じた光学系の選択が重要です。特に高光量LED照明を備えたシステムは、安定した照明環境を提供し、測定精度の向上に貢献します。
また、試験範囲に応じた適切な視野角を持つカメラを選ぶことで、広範囲かつ精密なデータ取得が可能となります。
プラスチック材料の引張試験に用いられるISO 527やASTM D638に対応した非接触伸び計の中には、絶対精度1.5µm、相対精度0.5%といった高精度を実現する製品もあり、信頼性の高い変位計測が求められる用途に最適です。
チャックの種類と適切な選択方法
引張試験機のチャックは、試験片の形状・材質・寸法・破断荷重に応じて適切に選定する必要があります。一般的に、丸棒形状には丸材用チャック(例:TR型)、平板形状には平材用チャック(例:TF型)など、試験片の形状に合わせた設計のチャックが使用されます。
また、試験片の材質によっては、チャックのツメ(把持部)に超硬チップや電着ダイヤモンドを施したタイプを使用することで、滑りを防ぎ安定した把持力が得られます。
チャックごとに対応可能な最大荷重およびつかみ幅(厚み)などが定められており、試験条件に適した型番を選定する必要があります。短い試験片や中空構造、高硬度材料、樹脂材料など特殊な形状の試験片には、専用のチャックまたはカスタム対応が必要です。
適切なチャックの選定は、試験中の滑り・偏心・破断位置のずれを防止し、正確な試験結果を得るための重要な要素です。
データ処理・解析機能の比較
引張試験機のデータ処理・解析ソフトウェアは、試験の種類に応じて多様な機能を備えており、引張・圧縮・曲げ・ピール・サイクル試験など、幅広い試験に対応可能です。それぞれの試験に特化した解析項目に基づいて、正確な材料特性評価が行えます。
代表的な解析機能としては、弾性率、最大点、降伏点、破断点などの重要パラメータを自動で抽出する機能があり、データ処理の効率化に貢献します。頻繁に実施される試験条件をあらかじめ最大30件まで登録できる「クイックスタート」機能により、試験準備時間を大幅に短縮できます。
データのサンプリング間隔も柔軟に設定可能で、例えば島津製作所のTRAPEZIUMX-Vでは、標準サンプリングで10ms~10時間の4段階、高速サンプリングで1ms~150msの3段階が選択可能です。これにより、動的な材料挙動の詳細な観察が可能となります。
さらに、取得した試験データは、グラフ、試験条件、結果値、写真などを自由に配置できるカスタムレポートとして出力でき、視認性と報告性に優れた資料作成が可能です。
| 機能分類 |
主な特徴 |
| 標準サンプリング |
10ms~10時間、4段階切替可能 |
| 高速サンプリング |
1ms~150ms、3段階切替可能 |
| 対応試験種類 |
引張、圧縮、曲げ、ピール、サイクル試験 |
| レポート機能 |
グラフ、条件、結果の自由レイアウト |
運用面での重要ポイントを確認
引張試験機の運用面において、設置環境やメンテナンス、導入方法の選択は、測定精度と費用対効果に大きく影響する重要な要素です。ここでは、装置の設置スペースや環境条件、校正・メンテナンスの実施方法、そして新品購入・中古購入・レンタルといった導入方法の比較について詳しく解説します。これらの情報は、引張試験機を導入する際の意思決定や、長期的な運用計画を立てる上で必要不可欠な知識となります。
設置スペースと周辺環境の要件
引張試験機の設置には、装置本体の寸法に加え、試験片の出し入れや操作を行うための作業スペースの確保が重要です。卓上型の引張試験機では、設置面積として幅1.5m × 奥行1m程度が目安となります。
温度や湿度の管理も試験精度に大きく影響を与えるため、室温23±2℃、湿度50±10%以下の安定した環境が望まれます。特に弾性率や伸びなどの精密な計測には、空調設備による制御が不可欠です。
また、周囲からの振動による影響を抑えるため、1階または地下フロアに設置し、防振台を併用することが推奨されます。
電源については、多くの卓上型機種では単相100V/15Aで運用可能ですが、中~大型の試験機では三相200Vの電源が必要となるケースもあるため、事前確認が必要です。
さらに、データ処理用のPC、プリンター、ネットワーク環境の整備も必要となるほか、安全性確保のための作業動線や非常時の避難経路の確保も重要です。これらの環境要件を満たすことで、正確で信頼性の高い試験運用が実現します。
メンテナンスと校正の実施方法
引張試験機の精度を維持するためには、定期的なメンテナンスと校正が不可欠です。校正とは、計測器の示す値と標準値との誤差を確認する作業で、JIS Z 8103で定められた重要な品質管理プロセスです。
メンテナンスには、清掃、整備、消耗品交換などが含まれ、通常は年1回の実施が推奨されています(使用頻度や品質管理基準により、より短い間隔で行うこともあります)。特にロードセルやつかみ具の点検は重要で、これらの部品の状態が測定精度に直接影響を与えます。
校正に使用する標準器は、トレーサビリティが確立されていることが必須で、最終的には国家標準につながる体系が必要です。校正後は校正証明書が発行され、これにより測定値の信頼性が保証されます。
| 項目 |
実施内容 |
頻度 |
| 常点検 |
外観確認、動作確認 |
使用前 |
| 定期メンテナンス |
清掃、消耗品交換 |
年1回 |
| 校正 |
精度確認、証明書発行 |
年1回 |
コスト比較と導入方法の選択
引張試験機の導入方法には、新品購入・中古購入・レンタルの3つの選択肢があります。新品の引張試験機は、卓上型の小型機種であれば50万〜70万円前後から販売されており、機能や構成によっては100万〜200万円以上となる場合もあります。
中古品は、新品価格の40〜60%程度で導入できるため、初期費用を抑えたい場合に有効ですが、校正状態や保証内容の確認が重要です。
レンタルは、卓上型で月額約15万円前後、フロア型で約25万円前後が相場であり、一時的な試験やスポット利用に適しています。ただし、長期間使用する場合は、購入の方がコスト効率が良くなることもあります。
どの導入方法が最適かは、年間使用頻度や試験期間の長さ、予算、管理体制などに応じて判断する必要があります。また、複数メーカーに一括で見積依頼ができる「メトリー」などの比較サービスを活用することで、効率的な選定が可能です。
| 導入方法 |
メリット |
デメリット |
| 新品購入 |
長期的なコスト効率が良い |
初期投資が大きい |
| 中古購入 |
初期費用を抑えられる |
保証面に不安 |
| レンタル |
初期投資不要 |
長期利用でコスト高 |
主要メーカーの特徴と製品ラインナップ
引張試験機の主要メーカーとして、特色ある製品ラインナップを展開する3社を詳しく解説します。高温環境対応や微小試料の評価に優れたアクロエッジ、高精度な計測・制御技術に強みを持つ日本計測システム、そして幅広い価格帯と充実したサポート体制が特徴的なイマダの製品特性や導入費用、サービス内容について、具体的に見ていきましょう。各社の特徴を理解することで、用途や予算に最適な引張試験機の選定が可能となります。
株式会社アクロエッジ
株式会社アクロエッジは、高性能な小型引張試験機を提供する専門メーカーであり、特に微小試料の評価において優れた性能を発揮します。
高温環境下での材料評価に対応できるモデルでは、最大1500℃までの温度制御が可能です。また、10^-6 Paの高真空環境での試験にも対応しており、特殊環境下での高精度な材料特性評価が実現します。
同社独自の測定システムにより、試料中央部の物性変位を正確に観察できるほか、コンパクトな設計により実験室内での移動や他機器との組み込みも容易です。
測定データは自動で記録・保存され、試験プログラムの登録・切替にも対応しています。さらに、充実した保護機構により、安全性にも十分配慮されています。
簡単に持ち運び出来る高性能引っ張り試験機|小型引張試験機 (株)アクロエッジ
日本計測システム株式会社
日本計測システム株式会社は、高精度な計測・制御技術に強みを持つ引張試験機メーカーです。同社の製品は、微細な変形挙動の計測に対応できる非接触伸び計の搭載が可能であり、繊細な材料評価に適しています。
製品価格は、標準モデルでおよそ300万〜600万円程度、高機能・特注仕様では1000万円を超える構成も存在します。使いやすさと多機能性を両立した設計により、初心者から研究開発者まで幅広く支持されています。
また、特殊なチャック機構により、様々な形状の試験片に柔軟に対応可能です。卓上型を中心としたコンパクト設計により、限られたスペースでも設置・運用が可能です。
一部機種では、自動校正機能やPCとのデータ連携機能も搭載されており、測定信頼性とデータ管理の効率向上が図られています。
株式会社イマダ
株式会社イマダは、荷重計測器の専門メーカーとして、高精度な引張試験機を提供しています。同社の製品は、卓上型引張試験機では50〜70万円程度から、高機能モデルで200万円前後の価格帯となっています。フォースゲージやロードセルなど、幅広い荷重測定機器のラインナップを持ち、測定範囲も0.01N〜50kNまで対応可能です。
同社の特徴は、技術相談から特注製作、サンプル測定まで、包括的なサポート体制を整えている点です。また、デモ機の貸し出しや実験室での測定サービスも提供しており、購入前に実際の使用感を確認できます。
購入後のサポートも充実しており、修理・校正サービスはもちろん、操作方法を解説したユーザーガイド動画の提供や、各種証明書の発行にも対応しています。さらに、自動車部品から医療機器まで、幅広い産業分野での測定実績を持ち、業界特有の要件にも柔軟に対応可能です。
引張試験機はレンタルできる?
引張試験機は、購入だけでなくレンタルでの利用も可能です。導入コストの削減や一時的な利用ニーズに対応できる選択肢として、多くの企業に活用されています。ここでは、レンタルを検討する際の判断基準、具体的なメリット、そして注意すべきデメリットについて詳しく解説します。希少な高性能機種から汎用的な卓上型まで、様々な機種がレンタル可能です。
引張試験機をレンタルにする判断基準
引張試験機のレンタルは、使用頻度や予算、運用期間などに応じて慎重に判断することが重要です。
一般的なレンタル料金の目安は、卓上型で月額15万円前後、フロア型で25万円前後です。年間の使用頻度が4回以下のスポット利用の場合は、購入よりもレンタルの方が経済的になることが多いとされています。
また、一時的な研究プロジェクトや製品開発段階での試験、評価用の短期使用にはレンタルが非常に有効です。レンタル機器は通常、事前に校正・整備済みで提供されるため、ユーザー側での校正・メンテナンス費用が不要という利点もあります。
一方で、最低レンタル期間は1週間〜1ヶ月とされている場合が多く、数日だけ使用するような短期利用には不向きです。また、人気機種は予約で埋まっていることもあり、急な試験需要に対応できない可能性もあるため、事前のスケジュール調整が重要です。
引張試験機をレンタルする場合のメリット
引張試験機のレンタルには、多くのメリットがあります。初期投資を抑えられることが最大の利点で、新品購入時の数百万円から数千万円の費用が不要です。また、メーカーによる定期的なメンテナンスや校正が含まれているため、精度管理の手間も省けます。
機種の選択肢が豊富なことも魅力です。大手レンタル会社では、複数メーカーの様々な容量・仕様の機種を取り揃えているため、試験内容に応じて最適な機種を選択できます。
さらに、専門スタッフによる技術サポートが受けられる点も重要です。操作方法の指導から試験条件の設定まで、経験豊富なスタッフのアドバイスを得られます。トラブル発生時も、迅速な対応が期待できます。
引張試験機をレンタルする場合のデメリット
引張試験機のレンタルには、いくつかの懸念点があります。搬入・設置には専門の技術者が必要で、これらの費用が別途発生する場合があります。また、試験機の改造や特殊な試験条件への対応が制限されるため、研究開発での柔軟な使用が難しくなります。
長期的に見ると、レンタル料金の累計が購入費用を上回る可能性もあります。3年以上の継続使用では、月額レンタル料金の累計が購入費用に匹敵するケースも少なくありません。
さらに、人気機種は予約が集中するため、希望する時期に必要な機種が確保できないリスクがあります。特に年度末など、需要が集中する時期は要注意です。
引張試験の外注
例えば自社で試験を行うことが難しい場合には、引張試験を委託することもできます。
株式会社神戸工業試験場(兵庫県)では、JISやASTMなどの規格に準拠した一般的な引張試験のほか、高温環境や大型試験片など特殊条件下での試験にも対応しています。
同社では、材料から製作した試験片に対し、JISなどの規格に準拠した試験機および試験手法を用いて、精度の高い引張試験を実施しています。試験片の寸法計測や標点距離の設定後、形状や材質、温度に応じて適切なひずみ取得方法(伸び計法またはひずみゲージ法)を選定し、規定速度で試験を行います。試験後は測定結果を整理し、報告書の作成まで行います。
神戸工業試験場|引張試験
まとめ
引張試験機は、材料の機械的特性を測定する重要な試験装置です。JIS規格に準拠した各種試験に対応し、高精度な計測・制御機能を備えています。非接触伸び計の採用や小型設計により、操作性と利便性が向上。主要メーカーは多機能性とシンプルな操作性を両立した製品を提供しています。
価格面では新品購入の他、レンタルや中古機器の活用も選択肢となります。導入時はチャックの選定や校正方法など、具体的な運用面での検討も重要です。極限引張強度(UTS)の測定精度を確保しながら、効率的な試験運用を実現することが、引張試験機選定のポイントとなります。